第2回 「グローバルなモノづくり」とは、世界を見据えた「ト ータルなモノづくり」と考えよ 前編

ラティス・テクノロジー/代表取締役社長 鳥谷浩志氏 × レクサー・リサーチ/中村昌弘
今回お越しいただいたラティス・テクノロジー(https://www.lattice.co.jp)の鳥谷浩志社長は、日本発のオリジナル3D技術を開発し、設計・製造領域におけるデジタルエンジニアリングの世界をリードしている。とくにXVLという超軽量3Dフォーマットを設計と製造分野に持ち込み、生産現場を変えていこうと日々邁進されている。XVLでは、3次元CADデータを1/100程度のサイズに軽量化できるだけでなく、3D形状に加えて属性情報、構成情報という3次元CADデータに含まれる情報をあわせて表現することが可能だ。そのため設計、製造、生産技術、サービス、調達といった各業務の目的にあわせて3Dデータを有効活用できる。
当社も仮想工程計画・生産ラインシミュレータ「GP4」を開発し、また、最近ではクラウド生産シミュレータ「GD.findi」を展開している。領域は工程設計と少し異なってはいるが、鳥谷さんが開発された技術の素晴らしさや、製造業におけるデジタルエンジニアリングの導入の難しさをよく理解している。こうしたことを背景に議論を進めていきたい。

超軽量3Dフォーマット「XVL」開発の背景
中村 皆さんもよくご存じだと思いますが、最初に御社の技術とその開発の経緯について、鳥谷さんからご説明いただけますか。
鳥谷 最近、製造業では3次元CADが普及してきていますが、多くの場合、設計者しか3次元CADデータを利用していません。2000年頃は、CAD/CAM/CAEにより、設計部門を主体に3次元データは利用されていました。当時、これが広がらない最大の原因はデータの重さにあるのではないかと考えていました。そこで、1997年に当社を創業し、データを軽量化することで、誰もが手軽に3次元データを使えるようにすることを目指す「Casual 3D」という新たなコンセプトを打ち出しました。まだ、インターネット接続も電話回線が主流で、ネットワークがまだ細かったので、徹底的にデータを軽量化し、誰でも3Dデータをネット共有できるような技術としてXVLを開発したのです。
中村 ユーザの反応はいかがでしたか?
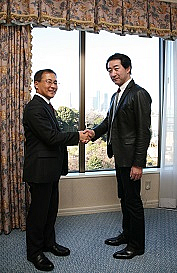
鳥谷 実際に製造業に持っていったところ、当初はデータが軽いというだけで大きな反響がありました。われわれが最初に手がけたXVLのバージョンでは、データサイズを軽くして製造部門などのパソコンでも表示できるようネットワークでの転送を高速化しました。デモをする度に、ネットでもここまでの3Dデータが転送できるのか、と驚かれました。しかし、3次元CADの普及に伴い2003年頃にはニーズが変化します。たとえば車では、1台分の3次元CADデータが10ギガバイトを超えるサイズになります。そこで、XVLの2番目のバージョンでは、10ギガバイトのデータを32ビットのPCでも扱えるようにするために、省メモリ性と高速表示を徹底的に追求したのです。そうこうするうちに、トヨタさんなどに代表される大規模メーカから「もっと大きな3Dデータを扱ってほしい」というご要望をいただく一方、ボーイングさんのような航空機メーカからは「ネット環境の貧弱な世界中のさまざまな空港でアクセスするので、もっと3Dデータを小さくしてほしい」という矛盾するニーズが寄せられました。そこで最新バージョンでは、その2つの技術を統合して、非常に軽くて大容量なデータを扱えるXVL技術を確立したのです。その結果、製造やサービスを始めとするさまざまな分野で3次元データが扱えるようになってきました。
中村 なるほど。当初、設計データの軽量化という方向に行かれたものの、製品の提供が進むにつれて、さまざまな課題が生じ、さらなる技術の進化を進めているということですね。今インターネットの世界では、データ転送能力やCPUの処理能力が高まっていますが、とくに製造業で対象になるデータは、ネットワーク回線の転送能力にくらべてまだまだ巨大だということですね。
鳥谷 そうですね。まさに中村さんが今、言われたところがポイントで、最近ではネットワーク回線も太くなり、PCのメモリも大きくなり、64ビットPCも出てきています。そのため私も会社を作ってから「いずれXVLという技術は必要とされなくなるのではないか」と危惧していましたが、実際には逆の方向に進んでいます。たとえば車の3次元データについても、製造業のグローバル化などによって、さまざまな車のバリエーションが必要とされるようになり、当初は1台で10ギガバイト程度だったものが、20、30ギガバイトとますます大きくなっています。それに加え、たとえば3Dデータを生産技術部門で使おうと思うと、今度は3万点の部品に加えて、さまざまな組立工程の情報まで入ってくるというように、さらにデータの大規模化が進んでいます。
中村 それはやはり、3次元データ技術の可能性が市場から注目され、ニーズが顕在化してくる中で、ユーザからの要求も多岐にわたっているからですね。
鳥谷 その通りです。また、もう一方の技術動向として、タブレットやスマートフォンがどんどん普及していますが、モバイル機器は逆にメモリが少ないのです。iPadの第1世代では256メガバイト、第2世代では512メガバイトしかないと言われていますが、そういうメモリの少ない環境で3次元データを見たいとなると、軽量性や省メモリ性がますます重要になるわけです。上流の設計部門では大規模データで検証し、下流ではタブレットなどで簡単に3次元データにアクセスするというように、製造業の上流・下流両方のプロセスでXVLの技術が必要になってきていると感じています。
日本の製造業が抱える課題

中村 つまり、XVLはこれからますます求められる技術だということですね。そういう鳥谷さんのご活躍の中で、製造業にも接点が広がり、お客様の現状や課題を把
握されていると思います。鳥谷さんも私も、ある意味、同じ立場で、デジタルエンジニアリングを用いて製造業のさまざまな業務や現場をどう効率化し、インボルブし
ていくかを考えているわけですが、お客様の内部をいかに課題していくかが重要なポイントだと思います。今、日本の製造業ではさまざまな課題が積み上がっている
のではないかと思いますが、そのあたりの鳥谷さんのご理解や認識について、少しお話しいただけますか。
鳥谷 現在の製造業が抱えている課題について、3つの観点からお話ししたいと思います。第1に、これまで日本の製造業はQCD(品質、コスト、納期)の改善を得意とし、現場のカイゼンを通じて生産効率や品質を向上させてきました。ところが、今デジタル家電産業などを見ていると、そもそも「何を作るのか」とか「どんなサービスを提供するのか」ということのほうが、より、問われています。自動車のように競争力の高い産業もありますが、かつての自動車・電機という日本の産業における二大巨頭のうち、電機はかなり弱くなっているわけで、新しいビジネスモデルに
加え、新しい製品として、何を作ったらいいのかが問われているのではないかということが、1番目のポイントす。
中村 そうですね。
鳥谷 2番目のポイントは、以前の円高から、アベノミクスで急速に円安基調に変わりました。この為替相場の大きな変動にどう対応していくかです。1番目の課題は「何を作るか」だったのですが、今度は「どこで作るのか」という新たな課題が生じています。実際、日本で作るのか、あるいは海外で作るのか、というところが問われていまして、製造業の最適配置と言いますか、生産地を臨機応変に移していくのがいいのか、それとも国内でじっくりやっていくのがいいのかという、役割分担がかなり重要になってきています。
中村 はい。
鳥谷 3番目はやはりグローバル化で、日本のマーケットは飽和状態にありますから、新興国で売れるもの、もしくは欧米で売れるものを作っていかなければいけません。そうなると、設計や生技(生産技術)あるいは生産部門に、いろいろな国の人が入ってくることになりますから、文化を超えて、日本のモノづくりを伝えることが大事になってきています。
中村 まさしく、製造業を取り巻く環境は大きく変わっていて、グローバル化や製品戦略に加え、社内の体制をどう改革するかが喫緊の課題になっています。こうした状況の中で、日本の製造業が変化に対して十分に対応できているかと言えば、そうでもないという現状があるわけです。その辺りの背景や原因について、もう少し議論したいと思うのですが、鳥谷さんのご意見やお考え方についてお話しいただけますか。
鳥谷 もともと日本人は「すり合わせ」のモノづくりが得意だと言われていました。今、その結果として残っている元気な産業と、元気ではない産業を見てみると、元気な産業は開発期間がある程度見込め、じっくりディスカッションしながら製品を作り上げていくようなやり方をしています。製品寿命も5年や10年、あるいはそれを上回るもので、かつ、カスタマイズ品主体、量生しても数万台程度のものが合っているのではないでしょうか。逆に、コンシューマー向けの最終製品として一気に投資を行い、何億台も作るようないわゆる「軽薄短小」の製品は、苦手になってきているのでしょう。昔、「軽薄短小の時代」と言われたこともありますが、これからは「重厚長大の時代」に戻ってくるのではないでしょうか。
中村 なるほど。
鳥谷 いずれにしても今、成功しているのは、製品を売るだけではなく、さまざまなサービスを組み込んでいるビジネスモデルが多いと思います。
中村 最初にご指摘いただいた点については、PDCAや現場力が日本のモノづくりの強さだとした場合、それらで対応しうるビジネスモデルや商品、あるいは生産量といった形態の中で、カイゼンなどで高い競争力を維持していけるものについてのみと思います。ところが逆に、生産量が少ない場合や、生産期間が短い場合、また、「すり合わせ」なしで作れるものについては、日本の強さが生きないということですね。
鳥谷 その通りです。
中村 それからサービス面では、ソニー対アップルという比較に象徴されるように、日本企業がグローバルにサービスをなかなか展開できない理由や背景、課題などがよく指摘されますが、そのあたりについてはいかがですか?
鳥谷 日本企業は地道な改善は得意でも、製品全体に関わるビジネスモデルを構築するとか、ソフトウェアを主体とするようなものは苦手だったのではないでしょうか。その一方で、コマツさんの「KOMTRAX」のように、数十万台の建機にGPSをつけた例もあります。最近IoT(モノのインターネット)のような技術も出てきていますが、ああいうものをどんどん工夫して採り入れれば、日本の産業はまだまだ勝てると思います。とくに数のシェアを持っている企業にとっては、それが大きな資産になってくるはずです。
中村 私も、その点についてよく考えることがあるのです。そもそも日本人は新しいアプローチや挑戦が得意なのかという議論もありますが、こと製造業では、そういう活動がやりにくくなっている状況にあるのではないかと、私は感じています。
鳥谷 なるほど。たとえば、どういう点でしょうか。
中村 とくに、株主資本主義とは言わないまでも、「ROI(投下資本収益率)をどう上げるのか」というように、さまざまな立場で経営を考えていこうとするとき、直接コストと間接コストを仕分けていく中で、間接コストを抑える動きがどうしても起こります。何が直接で何が間接なのかという議論もありますが、たとえば生産技術が間接部門だと理解されてしまう状況があるわけです。以前は大手メーカには開発部、生産技術部、製造部がありましたが、今、生産技術部を持っている会社は少数で、生産技術部の解体にともない、多くの人が設計部もしくは製造部の生産技術課に移っていった経緯があります。
鳥谷 そうですね。製造業の競争力の源泉であった生産技術は大事にしたいところですが、現状はどうなのでしょうか。
中村 いまや生産技術課は、生産技術や工法開発ではなく、設備の開発やインストレーション(据え付け)というオペレーションを手がける部署になっています。モノを
作るための手法を開発するミッションが解体され、会社としての、作るという意味での強みを構築する部署がなくなってきているのです。
鳥谷 そこまで退化しているのですね。
中村 その意味で、間接部門に真の強みがある会社は数多くあります。ところがその強みも、ROIで見てしまうとなかなか評価されません。こうした経営環境の中
で、製造部門で起きた問題を解決したり、新たに生産革新を行うための起点となる部署や人材、すなわち、モノづくりのノウハウが失われてきているわけです
鳥谷 表の競争力と裏の競争力と言いますが、裏の競争力の部分ですね。

中村 はい。その部分で課題を抱えている企業が多くなってきていると思います。それから現在の状況では、製品体系の中で派生品などがいろいろ出てくるようになると、それぞれを製品化するための生産技術や製造におけるノウハウ、バリエーションも広範囲にわたりますから、個人の力や経験だけではとてもカバーできなくなってきます。昔は、自動車メーカのラインナップで言えば、たとえば「カローラ」を含めて数種類で済みましたが、今ではいろいろな派生品が出てきているので、個々の経験では各製品の生産技術や製造をカバーできない状況に陥っていると思われるのです。
鳥谷 確かに、日本の生技のキーマンだったような人たちが、どんどん海外に行き、日本になかなかそういう人材がいないということが起こっています。その辺を、われわれのデジタルエンジにリングでカバーできるといいですね。
中村 そうですね。これまで上流も下流も、ある意味で設計も、属人的な能力で現場を回してきたと思います。ところが今、企業が対応すべき製品のバリエーションの幅や点数に加え、モノを作る場所も大きく変わっています。従来は、現場が見えている国内の工場で作っていたのに、今度はそれを海外の見ず知らずの工場でやらなければならなくなりました。しかも日本のスタッフが現地に行って見ているかというと、必ずしもそうではない。そのため、ますます生産現場が遠くなり、目が届きにくい存在になっていて、問題がボロボロ出てくるという状況ではないかと思います。そこで、デジタルツールをどう使っていくかが重要になります。日本のモノづくりの今後を考えると、今まで通りのやり方でいいというわけにはいかないでしょう。競争環境も、企業がやるべきことも変わっているので、それに合わせた体制や手法を構築していかなければなりません。
鳥谷 その通りだと思います。製造業はどんどんグローバル化していますから、現地に合った製品を作っていく必要もありますし、それに応じた開発体制、情報共有の体制も構築しなければなりません。その面で「こんなはずではなかった」ということが、現場で起きているとよく聞きます。言語の問題もありますが、文化の問題がもっと大きく、「日本人だったらそこまで考えてやるだろう」ということが、まったくなされていないということもあるようですから、その部分をしっかり伝えていくことが必要ではないかと思います。
中村 その点で、XVLは大きな効果を発揮する1つのプラットフォームになるのではないですか?
1 / 4










