第2回 「グローバルなモノづくり」とは、世界を見据えた「ト ータルなモノづくり」と考えよ 後編

ラティス・テクノロジー/代表取締役社長 鳥谷浩志氏 × レクサー・リサーチ/中村昌弘
今回お越しいただいたラティス・テクノロジー(https://www.lattice.co.jp)の鳥谷浩志社長は、日本発のオリジナル3D技術を開発し、設計・製造領域におけるデジタルエンジニアリングの世界をリードしている。とくにXVLという超軽量3Dフォーマットを設計と製造分野に持ち込み、生産現場を変えていこうと日々邁進されている。XVLでは、3次元CADデータを1/100程度のサイズに軽量化できるだけでなく、3D形状に加えて属性情報、構成情報という3次元CADデータに含まれる情報をあわせて表現することが可能だ。そのため設計、製造、生産技術、サービス、調達といった各業務の目的にあわせて3Dデータを有効活用できる。
当社も仮想工程計画・生産ラインシミュレータ「GP4」を開発し、また、最近ではクラウド生産シミュレータ「GD.findi」を展開している。領域は工程設計と少し異なってはいるが、鳥谷さんが開発された技術の素晴らしさや、製造業におけるデジタルエンジニアリングの導入の難しさをよく理解している。こうしたことを背景に議論を進めていきたい。

「捨てるべきもの」、「活かすべきもの」
中村 この対談の最初で、今の日本では新しいアプローチに挑戦するのはなかなか難しいという指摘をさせていただきました。今のお話を伺って、改めて考えさせられるのですが、実際に多くの日本企業は、新しいプロセスを活用して製品を市場に送り出すところまで、なかなか到達できていません。そこの差とは何なのでしょう?
鳥谷 今の例でいくと非常に簡単で、日本人がこだわったからですよ。日本人はパーツカタログのイラストの分解図や分解線について、「もっとこのように分解すべきだ」とか「線をもっときれいにこう描くべきだ」というように、必ず手修正を入れるのです。ところが手修正を加えると、パーツカタログ作成が自動化できません。私はドイツのパートナに「ドイツ人はそれでいいのか」と聞いたら「これでいい」と言うわけです。さらにその目的を尋ねると、「部品がわかればいい。なぜ、そんなところの線まできれいにする必要があるのか」と質問されました。そういう考え方が、日本で受け入れられるかどうかは、これからの話ですけれども。
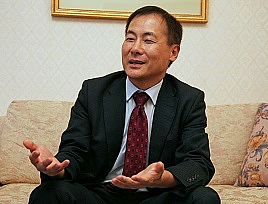
中村 そこはいい意味でのこだわりなのですが、逆の意味で言えば、そこで引っかかっているものがあるわけです。捨ててもいいことなのですが、こだわり続けている。良い意味でのこだわりではなく、悪い意味でのこだわり。
鳥谷 しかも、こだわっている人が、エンドユーザではなくて作り手なのですよね。エンドユーザはもしかしたら、自分たちが買うものが安くなるのであればこれでいいと言うかもしれないのですが、作り手側が「今まできれいにイラストを描いてきたのに、なぜこんなに簡略化するのか」と、こだわってしまうのです。
中村 そういう細やかな部分を追いかけようとするところが日本の強みでもあるわけですが、一方で、切ってしまってもいい部分を切ることができないという日本人特有の行動がありますよね。そういう、追いかけるべきものと、捨ててしまってもいいものを、投資効果のような経済的観点ではなく、エンジニアリング視点で検証できるではないですか。
鳥谷 むしろ経営的判断ではないでしょうか。先のパーツカタログのようなシステムを、あるアメリカのお客様で先行的に構築したことがあるのです。そのお客様は、何千社にのぼるユーザに製品を少しずつカスタマイズして届けていますから、自社に現物がありません。そのため、製品に不具合などがあってお客様から電話がかかってくると、何千枚もの図面の中からお客様のものを探し出し、不具合の原因を一生懸命調べていたのです。そこで同社では従来の体制を一新し、サービス担当者が、XVLの3次元データをもとに作成したサービスマニュアルを見て、電話をしながら「この辺を見て下さい」「ここを開けて下さい、こうなっていませんか」「この部品なら今発注します」という対応を行っています。お客様は実物を見ている一方で、サービス担当者はバーチャルモデルを見ながら、サポートレベルを大きく向上させました。今後は、そういうサポートに課金するなどの新しいビジネスに挑戦する視点が必要かもしれません。
中村 XVLに力や可能性があるからですね。
鳥谷 ありがとうございます。お客様も工夫次第で、いろいろな価値を生み出せるという点が重要です。
中村 それがXVLの素晴らしい点ですね。XVLならデータのサイズを気にせず、お客様が持てるデータを活用できますが、一般的な技術ではそうではなく、どこかにスレッシュホールド(threshold)、つまり論理的な閾値があるはずなのです。データ入力の精度とか、粒度と言ってもいいかもしれませんが、どうしてもそこにこだわってしまう部分がありますね。
鳥谷 まさに、軽量で高品位のモデルが保持できるところがXVLの最大の特徴です。
中村 実際に今動いているラインや製品の設計について「このままでやっていかなければならない」という、ある意味でのこだわりを、どうしても言いがちですね。でもそれでは、システム全体を系として見たときに、効果がないものを入れてしまうことになります。そのあたりの判断力、もしくは論理思考能力が弱いのではないかという気がしますね。
鳥谷 なるほど。
中村 職人芸ではなく、あくまでエンジニアリングの世界ですからね。グローバルの意味を「世界」ではなく「トータルなモノづくり」だと考えたときに、論理思考の視点が必要になります。そういう論理思考と、日本人がずっとこだわってきた現場思考を融合させていくというアプローチが必要だと思います。これは決して、現場思考は不要で論理思考だけでいい、ということではありません。現場思考にこだわっていては出口がない一方、論理思考だけでは日本の強みを活かせません。どちらを捨てて、どちらを取るかということではない、というメッセージを発信していくことができればと、つねづね個人的には思っているのです。
鳥谷 当社の製品の中に、3次元データからイラストを作る「イラスト作成オプション」というソリューションがあるんです。取扱説明書にもサービスマニュアルにもイラストが数多く入っていると思いますが、今まではそういうイラストを、実像を見ながらテクニカルイラストレーターが手で描いていました。ところが3次元データを使うと、全自動でイラストが作成できるので、経費が圧倒的に下がるのです。あくまで作業が理想的に進めば、の話ですが。ところが、実際にこういうソリューションを現場に持って行くと、「イラストを描いて生計を立てている人たちをどうするのか」という話になるわけです。
中村 そういう人たちがいますね。

鳥谷 たしかにそういう人たちが手で描いたイラストのほうがわかりやすいし、品質の高いものができているのは事実です。でも、モノがわかればいいというレベルなら、3次元データから自動的に作成した画像でも十分なのですし、コストもはるかに安い。そこでどちらを選ぶのかという話になると、やはり経営判断になると思い
ます。3次元データでやると決めたらイラストを描いていた方々には新たな価値を持ったマニュアル作成というより創造的な仕事に取り組んでもらえばよいでしょう。
中村 つまり、企業のあるべき姿というか、戦略が問われることになると思うのですが、そういう局面が、今後どんどん出てくるでしょうね。
鳥谷 そうですね。あるお客様では、思い切って、イラストは全部XVLを利用して作ることに決めました。ところが実際にそれをやってみると、問題が数多く起こるんです。たとえば、製品の3次元データが全部揃うとは限らない。サプライヤから調達した部品に3次元データがないということはよくあるからです。そうなると「3次元データの充足率は70パーセントぐらいしかありません。したがって、効果はこれぐらいしか出せません」ということになるわけです。そのため3次元データがない部品をどうするのか、手で描くのか、というように問題がたくさん起こるのです。
中村 そうでしょうね。
鳥谷 でも結果的にそのお客さまがどうなってきたかと言うと、3次元データがない部品については少しずつ設計部門でデータを作成するとか、提携部品の3次元データは購入担当部門で用意する、などの対応を行って、3次元データの充足率がどんどん向上しました。その結果、「だったら、こういうところでも3次元データが使えるじゃないか」という形で、デジタルエンジニアリングのスキルが高まっています。設計主導ではなく、後工程から「3次元でデータを持ってきてくれ」と設計に要求していくという形で、3D化が進んでいるのです。
中村 後工程から変わっていくというところが、素晴らしいと思います。XVLの効果を体感し、真の価値を理解したうえでの要求になってくるわけでしょうから、後工程から要求が上がってくることには大きな効果があります。たとえば、手でイラストを起こしていた人たちが、これから新しい技術にキャッチアップしていくという意味でも。
鳥谷 その通りなんですよ。
中村 本来はセーフティーネットも考えていかないといけませんが。
鳥谷 まさに今、それを提案しています。イラストを手で描いていた方が、アニメーションを定義するなどの仕事をしていくことで、3次元データを活用した次世代のマニュアルをiPad向けに発信しようといった動きです。
中村 今後そういう課題が、いろいろな領域で出てくると思います。デジタル化するということは、必然的にそういう部分を伴いますから。
1 / 3










