第4回 「価値づくりの突破口はモノづくりにこそある

一橋大学イノベーション研究センター長 延岡健太郎氏 × レクサー・リサーチ/中村昌弘
延岡さんは広島の出身で、1981年に大阪大学工学部精密工学科を卒業し、マツダに入社、同社で商品戦略を担当したのち、88年に米国マサチューセッツ工科大学(MIT)で経営学修士(MBA)を取得し、93年に同校でPh.D.(経営学博士)を取得。その後、神戸大学経済経営研究所の助教授、教授を歴任。2008年に一橋大学イノベーション研究センター教授、12年同センター長に就任し、現在に至る。近著に『価値づくり経営の論理』(日本経済新聞社)がある。延岡さんはこれまで、製造業における価値づくりについて数多くの提言を行ってこられた。日本のモノづくりは「価値づくり」に貢献できていない、機能的な価値だけではもはや競争に勝つことはできないという視点から、日本の製造業に警鐘を鳴らしている。延岡さんとともに、「今からのモノづくり」および「プロフェッショナルの知とデジタルエンジニアリング」をテーマに議論を進めていく。

価値づくりのために、モノづくりをどう活用するか
中村 延岡さんはMITに在学中、「リーン生産方式」という言葉が生み出された現場に居合わせたとお聞きしています。
延岡 当時、MITのビジネススクールに車好きが(私を含めて)3人いて、その1人がジョン・クラフチックという天才的な人物でした。彼が世界の100近い工場を回って生産性を比較し、在庫が少なくジャスト・イン・タイムで、かつプル生産方式であるトヨタ生産方式(TPS)が最も優れていると結論づけたのです。MITのキャンパスがあるケンブリッジの中華料理屋で、TPSのように効率的な生産方式にどんな名前をつけようかという話になったのですが、たまたまテーブルの上に豚肉の料理が出ていました。そこで彼が「リーン(lean/贅肉の取れた)生産方式という名前にしようと思う」と提案し、われわれは「ダイエットだ、それはいい」といって笑った思い出があります。
中村 そうなんですか。
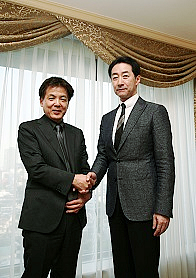
延岡 当時は80年代中盤でしたが、日本企業がまだ、日本流のモノづくりだけで競争力を維持していた良い時代でした。私もMITにいて非常に居心地が良く、日本人というだけで歓迎されました。「リーン生産方式」(が優れた生産方式として世界的に認められたことも)も、日本にとっては非常に良かったと思います。
中村 そうですね。
延岡 ところが1990年代中盤から、日本のエレクトロニクス産業が一気に競争力を失いました。薄型の液晶テレビや太陽電池モジュールなどで、日本企業が素晴らしい商品を開発しても、すぐに値崩れしてコモディティ化するというように、価値づくりができなくなったのです。そういう時代が、今に至るまでもう20年も続いています。今日はせっかく中村さんと一緒ですから、日本の製造業の課題である価値づくり、なかでも価値づくりにおいて製造、モノづくりがいかに重要かという話をしていきたいと思います。
中村 よろしくお願いします。
延岡 テレビもそうですが、商品開発だけによる差別化には限界があり、モノづくりを活かした価値づくりを行っていかなければ差別化は難しいというのが私の立場です。もっと長期的な話をすると、ミケランジェロの彫刻のような芸術作品を始め、陶芸品や家具、建築にしても、本当に素晴らしい商品は、設計開発も製造も一緒になって(価値づくりが)行われています。安藤忠雄さんの建築にしても、あの打放コンクリートという建物の作り方を含めたものが価値なのです。
中村 そうですね。
延岡 ところが産業革命を期に大量生産が始まって以来、商品づくりにおけるさまざまなプロセスや作業が無理やり分業化されてしまいました。いわば、本当に価値づくりができる人が、すべてにわたって価値を考える商品づくりを行うことができなくなったので、役割分担が起きたのです。ところが最近この分業の弊害が大きくなっていて、中村さんも手がけられているデジタルエンジニアリングなどを利用することで(商品開発と製造が)再統合される時代が訪れようとしていると、私はずっと主張しています。たとえば、先日「一橋ビジネスレビュー」の2015年春号で「デザインエンジニアリング」の特集を行い、アップルやダイソンなどを例に挙げ、デザインとエンジニアリングにおける再統合の動きを取り上げています。
中村 なるほど。
延岡 もう1つ、分業による問題点の解決ですが、設計と製造の再統合については、トヨタ生産方式も含めて、日本企業が中心となって比較的早く取り組みました。たとえば製造効率の向上やコスト低減、デザイン・フォー・マニュファクチャリング(製造性考慮設計)、すなわち作りやすさを意識した設計にすることで、問題を解決しようとしたのです。
中村 いわゆるDFMですね。
延岡 はい。主に製造効率を向上させるために、日本企業はとくにその辺をうまく調整して力をつけました。ところが最近、商品開発だけでは価値づくりができない時代になったので、効率化のためだけでなく、製造も設計も一緒になって価値づくりを行うという方向で、(設計と製造の再統合を)もう一回行う必要性が生じていると思います。
中村 そうですね。
延岡 かつて無理やり分業化されたものを再統合するうえで、私は技術が一番大事だと考えています。陳腐な例で言う
と、ワープロの登場によってタイプのオペレータが要らなくなったように、3DCADの普及で、CADオペレータもかなり減りました。そのように、新しい技術が生まれると、今まで分業しなければならなかったことが、ツールを武器にして統合的に行えるようになり、その結果、本当に価値の高い商品が生み出されるようになるわけです。

中村 なるほど。
延岡 その最もわかりやすい例がアップルだと思います。アップルの競争力を構成する要素として、OSなどももちろん重要ですが、私は少なくとも同社の競争力の半分以上が、非常に美しく、触っていても心地良いアルミ合金削り出しの筐体である「ユニボディ」にあると思います。アップルはこれを新機種が出るたびに数千万台レベルで製作していますが、本当にデザインが良いものを作ろうと思うと、プレスではほとんど不可能で。彫刻家がプレスで芸術品を作らないのと同様に、高精度の切削を行わなければ本当に美しい筐体は作れません。アップルがそういう作業を、数千万台というレベルで行っていることに改めて驚かされます。
中村 そうですね。
延岡 ユニボディを考案したのはジョナサン・アイブというデザイナですが、中国にあるホンハイ(台湾・鴻海科技集団/FOXCONN)の製造拠点に何カ月も入り浸り、製造方法の検討も含めてアルミ合金を削り出す作業を行っています。デザイナがモノづくりの部分にまで深く関与した結果、アップルは大きな価値を生み出したわけですが、本来は日本企業こそが、モノづくりの強さを価値に結びつけることを手がけなければならなかったという意味で、非常に示唆的です。
中村 なるほど。
延岡 日本はモノづくりに大きな強みを持っているのですから、価値づくりのために、モノづくりをどう活用するのかをよく考えるべきだと思います。
中村 私は、商品とその使い手であるユーザとの関係の中に、大きな価値が存在していると思います。当社は今年で設
立22年目を迎えましたが、20年前からコアテクノロジの1つとしてVR(仮想現実)という技術を追いかけてきました。それはなぜかと言うと、仮想化すること自体が目的ではなく、仮想化することによって、ユーザと設計物との距離が縮まるからです。バーチャル空間の中で、設計物が単に3次元になって見えるだけでなく、ユーザが自分で設計したものを、等身大の感覚で扱うことを可能にするためのVRであるべきだと言いつつ、ずっとその技術を追いかけてきたのです。
延岡 そうなんですか。
中村 そこで取り組んだのが、新たなユーザインターフェイスの構築です。人間の思考にそのまま対応し、直感的に操作ができる技術が必要だと考え、20年ぐらい前から研究開発を行っています。たとえば「3次元ドラッグ&ドロップ」という、当社が特許を取得した技術がありますが、これはバーチャルの3次元空間でモノをドラッグして動かすというものです。
延岡 そういうところに、大きなイノベーションがあるわけですね。
中村 はい。私が特許を出願するまでは、バーチャルの3次元の空間でモノを動かそうとするとき、CAD上ではX軸→Y軸→Z軸の順に物体を移動させて回転させるというオペ―レーションを取らなければなりませんでした。でもこれは人間の感覚から言うと非常に不自然で、ユーザにとってあまりにも不親切です。ユーザは画面上の「ここからここ」に物体を持って行きたいのだから、ドラッグ&ドロップがいいに決まっているのに、そういう技術が存在しなかったのです。
延岡 技術開発のハードルがかなり高かったのでしょうね。
中村 3次元空間とは言っても、画面上に見えているのは2次元映像ですから、2次元情報から、物体を移動させたい場所の3次元座標値を算出する仕組みが要るのです。すなわち、2次元空間から3次元空間に座標データを逆変換する仕組みが必要で、当社はその仕組みを特許化したわけです。そのアプローチは、ユーザの感覚と目的と意思に対応し、人間の操作と同じオペレーションで動かせること。ユーザとのそういう接点を、いかに作り上げるかが重要だと私は考えています。
延岡 今、商品開発で流行っているのが「デザインシンキング(デザイン思考)」なのですが、それは、商品で何ができるかではなく、ユーザインターフェイスを重視する考え方です。私は最近「デザイン価値」を研究する中で、見た目の美しさや、触ってみての心地よさ、持ってみての使いやすさといった事柄すべてがユーザインターフェイスであり、それらが同時に商品の価値であるという話をしています。とはいえ、デザインシンキングを実践するには、単に机上でこんなことができる、あんなことができるという設計だけでは話にならず、ユーザが商品のインターフェイスをきちんと評価できるところまで技術を高めなければなりません。まさに中村さんがいま手がけているような、製造の部分に加えて、モノだけではなくプロセスも含めたすべてをプロトタイピングできるような技術が、将来的には出てこなければならないと思います。
中村 そうですね。
延岡 そうなってくると、分業のやり方自体がガラッと変わるのです。価値を本当に理解し、価値を創る能力のある人が、すべてを統合的に見るということが、然るべきツールさえあれば可能になります。昔はレオナルド・ダ・ヴィンチのような天才でなければできなかったようなことが、ツールをうまく使えば、凡人でもできるようになるわけです。にもかかわらず、今もなお「ツールが設計と製造の間のコミュニケーションを促進する」という程度の認識で止まっている人が多いのですが、われわれが目指すべき次のステップは、本当の意味での(設計と製造の)統合です。
1 / 3










