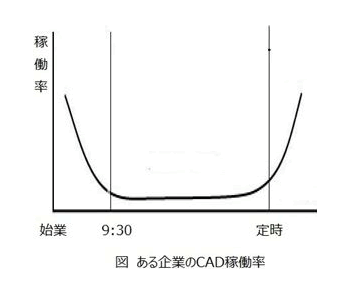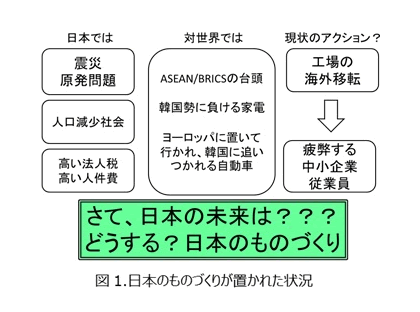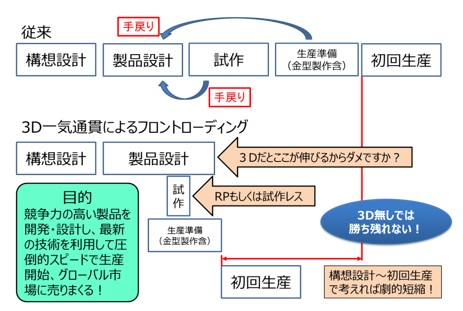ドイツの風 Vol.1 製造業のチャレンジ: ドイツの動向が刺激になる

激しい時代の変化に直面して悩むのは日本の企業だけではありません。「ドイツと日本は世界的に観ても似たような境遇にある。ドイツ人が何を考えているか物凄く興味がある。別の観点からの発想、刺激が喉から手が出るほど欲しい。」とは、私の知り合いのごく一部の人達の声でしょうか?長年日本が東の横綱であればドイツが西の横綱として世界の産業界をリードしてきました。そして両国が新しいチャレンジに遭遇しています。歴史、文化、宗教、習慣が全く違うが、世界的に見ると非常に似た境遇にあるドイツと日本です。どのようにチャレンジを克服しようとしているのか、興味があるけれど情報が乏しい。何か別の観点があれば、参考にしたい。行き詰まった自分の思考に、新しい刺激が欲しい!自分達に無い発想が有れば、その刺激が新しい構想展開の起爆剤になる。そのような期待に応える為に本ブログで情報発信を始めます。
似ているようで遠いドイツ
ボッシュグループの自動化機器メーカーの日本事業を立ち上げていた時期の話です。出張で日本からドイツ本社へ帰り、社長へ挨拶すると、まず行く先はサービス部門です。何か新しいトラブルがなかったか、そしてそのトラブルがどのように解決されたか確認しに行きます。そして工場をひと回りして、配置が変わっていれば何故変更したか説明を聞いてから技術開発部へ顔を出します。日本とドイツでは顧客対応への考え方が違うので、丁寧に顧客の考え方を説明しなければなりません。
日本とドイツは非常に似ているようで、細かい点が大きく違います。そして、それを無視すると大変痛い失敗をします。世界中見回しても日本ほどドイツと違う国はありません。片方で似ていると主張しながら、片方で違うと言う主張は確かに矛盾があるように見えます。ですが、自動化技術メーカーの観点からしますと、日本ほどドイツから遠い国はないのです。ドイツメーカーが世界中どこへ行っても、顧客はドイツのスタンダードを認めます。ところが、日本は長年キリスト教文化圏外で唯一の高度な産業国の伝統と文化を築いた国ともいえます。ですから日本は独自の考え方を持っています。ドイツの技術開発部にとっては、日本が一番遠く、そして難しい市場なのです。

この記事の続きは、GD.findi サイト にてご覧いただけます。

著者情報
Ando Mahito
中学時代にドイツに渡航。カールスルーエ工科大学にて、機械工学を専攻の後、PhDを取得。卒業後は、シーメンス社やボッシュグループにて、プロジェクトマネジメントおよび経営企画、社内コンサルティングに携わる。
現在では、株式会社レクサー・リサーチ、フラウンホーファー財団IPA研究所と共同開発契約を結び、シミュレーション系最大手エンジニアリング会社と協力関係構築から生産シミュレータGD.findi のドイツ市場開拓に従事。