第4回:必要な初期在庫量を求めよう! ~GD.findi で見える中間在庫量とは?~

前回(中間在庫モデルを作ってみよう!在庫量モデルを作成する)では、 GD.findi の初期在庫を用いて後工程
の手待ちをなくす方法をご紹介しました。 また、当然のことながらこれに伴い、中間在庫量が増えてしまうこ
とも確認することができました。
今回は、工程間の能力差に対して「中間在庫量が増えすぎていないかどうか」、すなわち、後工程をフル稼働さ
せるために、「どれくらいの初期在庫が必要なのか」を求めてゆきます。する方法をご紹介します。
前回の Tech Magazine で作成した GD.findi モデルを使って中間在庫量を確認します。
前回の Tech Magazine はこちらをご参照ください。
▼第3回 中間在庫モデルを作ってみよう!在庫量モデルを作成する
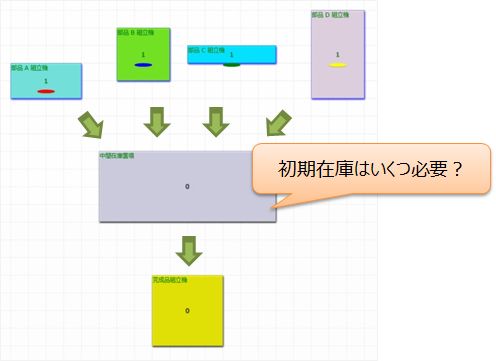
1 モデルのオープンとレンダリング実行
GD.findi にアクセス、ログイン後、前回のモデルをオープンし、 オープンしたモデルでレンダリングを実行します。
※ 新規ウィンドウで最初にレンダリングを行う場合は、先に [Reactorの起動] ボタンをクリックして、
[Reactor] タブを表示させてください。

2 中間在庫量の推移の確認
中間在庫置場の在庫数の推移を部品別に見てみます。
※ 在庫推移データは GD.findi のログファイルから生成
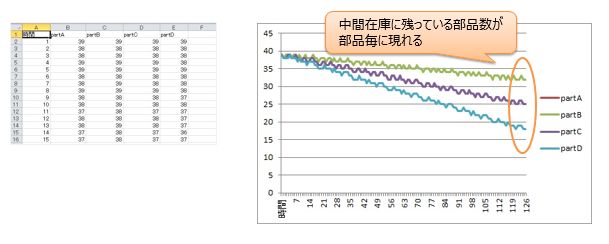
横軸 : 時間、縦軸 : 在庫数
partA : 部品 A 、 partB : 部品 B 、 partC : 部品 C 、 partD : 部品 D
各部品の在庫数の時間推移が表示されます。
※ 部品 A と部品 C は同じ在庫推移のため、重なって表示されています。
これより、生産終了時の中間在庫置場に、各部品が残っていることが分かります。
3 初期在庫の変更 では、 GD.findi で中間在庫における部品 A の初期在庫を減らしてみましょう。
ステーション「中間在庫置場」の部品 A の [初期在庫] の [部品数] を、半分の “20” としてみます。
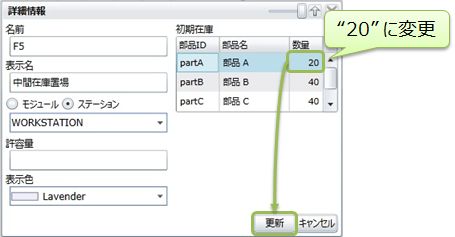
再度、レンダリングの実行 → ログデータから在庫推移データを生成を行って在庫の推移を確認してみましょう。
在庫推移グラフを見ると、部品 A の在庫量が少ない状態から減少する様子が見えます。
しかし、生産終了時点でもまだ部品 A が残っていることも分かります。
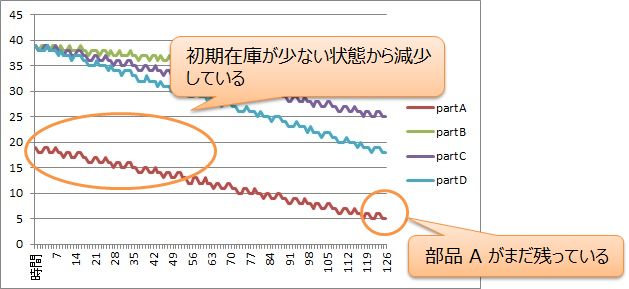
では、部品 A の初期在庫をさらに半分の “10” としてみます。
部品 A の初期在庫が 10 の時は、後工程の処理能力に部品 A の供給が間に合わず、手待ちが発生してしまうことが [Production Cockpit] 画面などからも分かります。
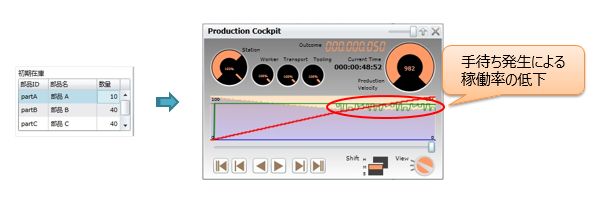
マテリアルフローで稼働状態を見ると明らかです。
マテリアルフローは [ツール] → [マテリアルフロー] をクリックすると表示されます。
稼働状態は、 [マテリアルフロー] 画面の [Station] 、 [Expand] 、 [Hide] チェックボックスをそれぞれ ON にすると見やすくなります。
[中間在庫置場] の稼働状態を見ると、非稼働(ピンク色)の部分があることが分かります。
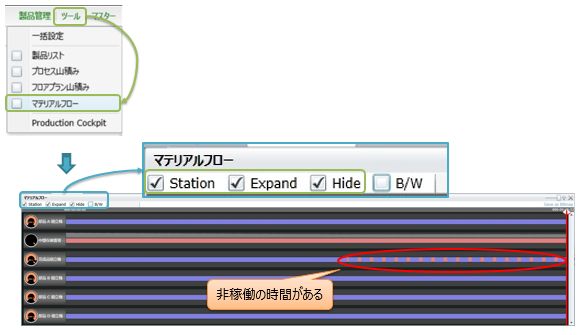
4 必要な初期在庫の決定
部品 A の初期在庫は 10 個では不足してしまいました。
これらから部品 A は最低でも 11 個以上、生産終了時に余らないようにするためには 19 個以下が望ましいことが分かりました。
このように、部品 A の初期在庫を、結果を見ながら増やしたり減らしたりして、必要な初期在庫数を絞り込んでいきます。
すると、部品 A の初期在庫は 15 個であれば過不足なく生産できることが分かります。
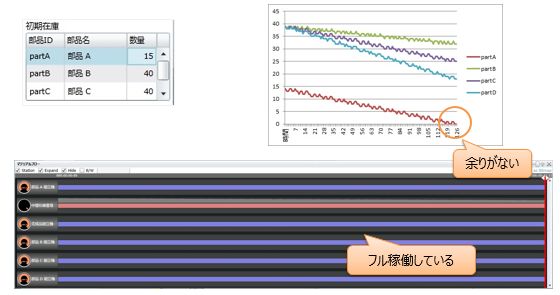
以上のことから、
部品 A と部品 C は 15 個、部品 B は 8 個、部品 D は 22 個の初期在庫があれば、後工程の手待ちも、生産終了時の中間在庫の残留個数も 発生しなくなることが分かりました。
第 2 回から 3 回にわたって、中間在庫量の決定プロセスをご紹介してきました。
今回ご紹介したモデルは、単純な生産システムのため、簡単な計算で求まる場合もありますが より複雑なモデルに対しても、今回と同様に在庫推移を観察し、初期在庫量を変動させることで、後工程の手待ちの発生を防ぐことができます。
また、次回からは、別の問題に対する GD.findi の活用方法をご紹介いたします。
なお、 GD.findi に関する詳細は下記ページよりご覧ください。










